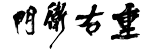雪舟 Sesshu
雪舟は、岡山県総社市の備中の赤浜生まれであります。地侍,小田氏の出身と伝わる。その父母、先祖、家庭の事情などは何も知られていません。生年は彼の作品に記されている年齢から逆算すると、応永二十七年つまり1420年となるが、詳しい月日はわからません。しかし、その小田氏の長子でなかったことは確かで、もし長子であったならば自家を継ぎ、武家になっていたはずであります。次子以降は、当時の習慣として若くして僧籍に入ったようであります。当時の武家階級の信仰として、最も身近にあり、また修業如何で自身の能力を発挿できる宗教といえば、それは禅宗であったのであろうか。禅寺自体が武家の庇護のもとに栄えた時でもあり、修業の傍ら、文芸的才能や外交的手腕を発挿するならば、出世の道も早かったのであります。雪舟は武家の子として、その何れかの道に頭角を現わしていたに違いません。
彼は、現在岡山県総社市にある宝福寺、これは臨済宗東福寺の寺派に属して、聖一国師の弟子の曇奄が開山であり、そこに入ったと伝えられます。そこで得度を授けられたのでしょう。涙でネズミを挿いたという説話がこの寺に伝わるが、これには確証がません。少年期に京都に上り、そして相国寺の春林周藤の弟子となった。その間の事情は、今だにはつきりしていないが、永享二年(1430)以降に相国寺の春林周藤のもとにいたことは事実のようであります。相国寺は正統な禅苑として当時栄えていた寺で、幕府直轄の寺でもあり、この正統な禅の大寺と雪舟との結び付きは、以後の彼の行動と修業の上に大きな役割をもたらしました。彼がついた師、春林周藤が相国寺の住持となったのは、永享四年(1432)であり、さらに周藤が鹿苑院の塔主となったのは宝徳三年(1451)、雪舟が32歳の時であります。つまり、この間に雪舟は京に上り、相国寺において禅を学ぶ傍ら、当時相国寺の会計役(都管職)であった周文らの活躍している時代であったから周文の画を見、あるいは学んだとも考えられます。この13歳から32歳の間、つまり少年期から壮年期に至る間の雪舟は、禅と絵画の両面の修業をしていたと考えられます。しかもこの間に、彼は師の周藤から「等揚」という諱をもらったのであります。
この等揚は、画の勉強に心を燃やし、周文並びにその大きな画壇的性格を持った周文派の画様を身に付けていきました。ここで大いに技術的な進歩が見られたわけであります。当時、幕府の政策として遣明船が往来していたので、その舶載文物としての絵画が身近にあったことも幸いしました。山水画、花鳥画、人物画などを見たり、あるいはそれらから画材を取ったものが多く描かれたであろうと思われるが、その作品は一作として残っていません。つまり等揚の修業期間中の状況については、資料的に何も知る由もないが、画僧としての修業は熱心であったようであります。後年にみせる彼の闊達な画法や、習練による画格は、修業時代に群を抜いて天才肌を見せていたことを物語るものでしょう。この前兆は等揚と交流のあった禅僧たちの著した文集にしばしば見かけられ、後にはかなりの画家に成長していったことも知られます。また雪舟がこのように画事に精通していった裏側には、相国寺という官寺に集まる禅僧らが、京都の五山や鎌倉五山の寺々や、その五山のもとの十刹などの寺からも京に上って来ていた、優れた禅僧らの密集していたことがあります。彼らもやはり修業し、後業成って故郷に帰り自国の寺の住職になる時には、相国寺で修業済みということが最高の名誉となり、彼らの多くは郷関でもてはやされたのでありました。禅僧ならばもちろん、画僧もその中に加わっていたことは想像に難くません。だが彼らの間にも、門閥関係の問題がありました。豪族の中でも名の知れた氏の出身であるとか、公家出身という格が京五山の住持になるためには必要であったようであります。だが、等揚には備中の地侍出身という、非常に低い地位しかなかったので、京都で禅僧として名声を博するには不可能に近い状態だった事は、当時の名禅僧になった人たちの背景を考えれば明らかであります。このことは、等揚自身よく知っていたに違いません。以後、彼の禅僧としての地位は知客でありました。知客とは接待役であって、禅僧の地位としては非常に低い地位にあたる。そして彼は僧侶間では、揚知客と呼ばれたのであります。
このような低い地位を身に背負ったまま、彼は一生を終るのであるが、そこで彼は彼らしい決断を自ら下したと解釈される。つまり禅僧として一つの規矩に縛られて、身動き出来ぬ枠にはめられていることへの反発として、絵画部門での画人としての生涯を全うしようと心に誓ったのでありました。これは彼の修業期、青年期、壮年期の現状を考えても明らかであり、加えて自身絵画的才能を認められて来た時にあたって、その方向に指針を合わせて行動に移した、と見るのはまず間違いはません。
では、等揚が画人としてはどのような心構えを持っていたのであろうか。先に等揚が周文についていたことは述べたが、これは当時の禅僧翔之慧鳳や了奄桂悟らの優れた僧たちから贈られた詩、文章によってその跡を知ることができる。そこには周文の弟子というよりも、むしろ如拙の孫弟子であると書かれています。如拙の画を大切に所持し、愛敬した事実によるのでしょう。その画は現存していないが、彼は終始如拙の画風に深く心酔し、慕っていたようであります。しかし、如拙に直接師事したのではなく、画を通じてのことでありました。また周文から諭されたこともあったに違いないが、それは画法、画事についてのみであったでしょう。如拙への深い私淑は、晩年に至るまで彼の画を持ち続けていたことでも裏付『けられます。また、如拙の画に慧鳳が賦した賛の中に「雲谷のこの画本を見る。箕裘なり、青氈なり」の一文があることからも頷ける。さらに、文明十二年(1480)の時、彼の弟子等悦に如拙の描いた「牧牛図」を画法の伝授として与えており、これもやはり詩僧として有名な村庵霊彦の賛によってわかる。これらの諸事実から考えて、直接師事した周文よりも、むしろ如拙その人と作品に示した熱情的な感応が、等揚の根底にあったことを知らねばならません。普通ならば、当面の師である周文からの影響や、私淑の方法があったはずであるが、一段飛び越えて先輩如拙の画事について考究し、研究したのでありました。
いうまでもなく如拙は、室町水墨画を規定した源泉であったばかりか、中国画摂取を果たし、自身の画風を確立した人物でありました。当時の水墨画壇の先駆者として認められ、「瓢鮎図」上の序文の筆者大岳周崇は「大相公、僧如拙ヲシテ新様ヲ座右ノ障屏ノ間二描カシム」と賦しています。この一文は、禅家独特の禅的内容とも解されるが、ここでは明らかに両様の新様を示していると解釈すべきで、これが当時の如拙評であったのであります。その新様は、等揚の若き心を揺さぶり、熱狂的な如拙崇拝者を作り上げたのであります。このことは、ただ画法授受だけに終らなかったようです。
Sesshu 雪舟
Wikipedia Sesshu
ウィキペディア 雪舟