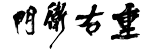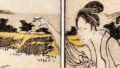写楽 sharaku
東洲斎写楽
この浮世絵師ほど多くの憶説につつまれ、数多くの研究家によって、その巨峯を踏破せんと試みられたものはありませんでした。出生をはじめとして、いかなる生い立ち、画界へのデビューと引退、妻子の有無、友人知己の消息、没年など一切不明であり、写楽の一生は霧中にとざされているといえましょう。そこにはただ寛政六年(1794年)から同七年の両年に描かれた、版画百四十数枚のきわめて特色ある作品が存在するだけです。写楽画と称する肉筆や版下絵もかなりの量が存在しています。しかしこれらについての真偽はまだ十二分の考証がなされず、真筆であると断を下すには、まだ早計の膀を甘受しなければなりません。
美術作品の認識は、その作家をあらゆる歴史的条件によって判断することにおいて始まります。しかし往々にしてこれがまったく行き詰まり、作家の人間性を把握するのに困難さを感ずることがしばしばあります。特に封建社会制度の機構に順応して発展していった近世江戸時代においては、その階級制度の下位に属する絵師などは、権門の武士や公卿と結託した狩野や土佐派の絵師を除けば、まったく歴史の塵埃ほどにも受け止められてはいませんでした。まして豪商などとはいわれぬ町人階級が、ほとんどの需要を担っていた浮世絵においては論をまつまでもありません。浮世絵師春信や歌麿ですら、社会的階級の点から役者を描くことに反発をもっていました。その歌舞伎役者が河原者と呼ばれ、蔑視されつつもそれを甘受して芸道一筋に励みぬいたのとは、いろいろの点において異なるとはいえ、その社会的身分は、やはり底部に近いものでした。野口米次郎氏の選出した浮世絵六大絵師すなわち春信・清長・歌麿の美人画家、役者絵師の写楽、北斎・広重の風景画家においても伝記不明の部分は大きく、年代考証などに勘案されるべき歴史的資料に欠ける面が多大です。特にこれらの世界的有名絵師のなかで、最も伝記が不明で、最も作品量の少ないのが写楽です。
世界に散在する浮世絵に対する研究は、日本人と外国人では自ら異なった方法をとることになります。日本人は古文書に強く江戸の文化を知り、歌舞伎や遊離の状態などよく理解できます。当時の演劇界、文壇などの関係筋の調査は、古文書に親しまぬ外国人では至難の道ですが、反対に浮世絵作品の収集においては比較にならぬほどの多くの名品、珍品を蔵し、数量的に多い外国では、様式研究が可能です。写楽も在外作品が多く、一枚しか発見されていない版画作品も在外に多いです。管見によればボストン美術館収蔵の写楽作品数は第一で七十数点、これに次ぐのがシカゴ美術館とニューヨークのメトロポリタン美術館の四十数点、ヨーロッパではイギリスの大英博物館とフランスのギメ美術館の二十数点がその大なるものといえましょう。さいわいなことに松方幸次郎氏がパリで買い集めた浮世絵版画が大正九年日本に帰り、現在東京国立博物館に温存されていますが、このなかに写楽が七十数枚あり、日本における写楽研究の宝庫となっています。さらにいまだ世界で唯一枚しか所在の知られてない写楽版画の数を調べてみますと、三十五点の多きをかぞえ、所在不明作品すなわち今迄写真その他で知られるのみの作が三点もあります。そして世界で唯一枚しかない作品をシカゴ美術館は八点、ボストン美術館と東京国立博物館は六点所蔵し、そのベストースリーに数えられます。西ベルリンの国立博物館の「四代岩井半四郎の信濃屋お半」、内山晋氏の「中島和田右衛門の丹波屋八右衛門」の世界で一枚の写楽版画を一点ずつもっているところもあります。
このように世界に散在している写楽作品の総合的研究には多大の時間と労力が必要であることは論をまちません。研究資料の多すぎる場合、その整理分析に多大の労力を費やし、求める純粋な事象はかえって把握し難いです。また反対に少なすぎる場合は、その極限されたもののなかから、人間の持てる想像力は、無限の天地に飛翔して、自由な人物構成をなしえられますものの、その翼をこわす危険率ははなはだ高いです。写楽研究はまさに後者です。いくつかの新説が世に発表され、まもなく泡沫のごとく消え、また新説が出るというのが写楽研究の現状です。巨峯写楽の究明に世界の浮世絵研究家は、歩みをせきとめられ、手のつけられぬ重みに娠りまわされているといえるのではないでしょうか。
寛政期の歌舞伎と浮世絵界
江戸開幕以来二世紀になんなんとする寛政年間(1789年-1800年)は、打ち続く太平とともに、幕藩体制に内在する矛盾が次々に表面化され、その危機を回避して、再建復興を企てねばならぬ時代となっていました。幕政改革といえば、一般に享保・寛政・天保の三大改革を指しますが、これは純粋封建体制の崩壊過程における必死の抵抗を意味しました。封建反動の車輪は、これらの歯止めをもって一時的なおさえにはなりえても、急坂をころげゆく勢いにはどうにもなりませんでした。田沼意次の側用人政治時代に後期が弛緩し、風俗が類廃し、鋭く露出した危機に対し、政争の形をとって徳川一門の粛正を行い、厳しい緊縮を断行した松平定信の政治が「寛政の改革」です。定信は社会の病根は奢侈にあると考え、奢侈の禁圧、風俗の矯正に重点をおきました。破魔弓・菖蒲刀・羽子板などに金銀箔を用いるのを禁じ、金の櫛や金の算をさすこと、煙管や手遊物同様の品に金銀の蒔絵を禁じました。男女混浴を禁じ、高価なる菓子の製造も禁じ、小袖表の代銀を三百匁、染模様の小袖を五十匁に制限しました。さらに華美にして高価な、そして好色狼雑な出版物を取り締まり、時事を一枚絵にして刷り出すことなども禁じられました。しかし「白河の清き流に水絶えて昔の田沼今ぞ恋しき」との民衆心理を理解できなかった定信に対する批判もかなり大きいものがありました。やがて定信が引退した後、世の中はまた自らにして往くべき道に向かって進行し、時代の流れは止めるべきもありませんでした。
松平定信は寛政五年七月老中を辞任し、将軍家斉の大御所時代が始まりますが、幕府は寛政六年十月、寛政元年発令の倹約令をさらに十年延長することを布告していますので、写楽の作画期の寛政七年は、この倹約令下の諸条件が未だ弛緩しない時代であったとみるべきです。翌寛政七年十月幕府は女髪結いに華美な髪形の禁止を布達しているのをみても、そのことが裏付けされましょう。幕府の緊縮政策がいきわたればわたるほど、市井の人々には不景気が激しく、物価が高騰し生活が苦しくなるのが常でした。
このような世情は歌舞伎界にもみられました。役者給金の高騰、座主の奢侈に加えて、寛政の取り締まりは手ひどく、伝統を誇る中村・市村・森田の江戸三座は五十万両の大借に身動きがとれず、中村、市村の両座はついに寛政五年の秋狂言を開くことが不可能になり、九月に出願して十月三日許可を得て、五年間それぞれの控え櫓である都座と桐座に興行権をゆずり渡しました。森田座は中村・市村の二座より先に、天明八年の顔見世が終わると不入りのため休座となり、寛政二年の顔見世からこれも控え櫓の河原崎座が興行を辛うじて行なっていました。かくて寛政五年の顔見世から江戸三座はともに控え櫓で興行が行なわれるようになりました。しかも皮肉なことに十月二十五日湯島雲州侯よりの出火のため焼け、仮普請でこの年の顔見世を行なったようです。このような寛政期の歌舞伎界の衰微は、見物料の暴騰にも原因があったようで、桟敷などをふやし収入面を考える一方、役者の給金も制限し、寛政六年十月には役者一年の給金最高額を五百両におさえることなどが行われた。当時最高の給金九百両だった瀬川菊之丞は四百両に、七十両とっていた中島和田右衛門は十両減らされるといったように、支出面も大きくおさえた経済をとり行わざるをえなかったのです。
このような経済的危機を背景にもった歌舞伎界ではありましたが、芝居の内容においては、名優が、よき狂言作者とともに輩出し、化政期の舞台を準備しました。特に写楽作品と対比して考察したいのは、芝居に現れた写実主義です。まず舞台装置に大きな進歩がみられること。すでに回り舞台、宙乗り、がんどう返し、丁字形の御殿のせり出しなどが実際に行なわれていましたが、寛政五年の『けいせい楊柳桜』のドンデン返し打ち抜きの造り物などでスペクタクルなものを形成してゆき、劇の進行に迫真を加えていきました。
演技面でのリアリズムも『五大力恋絨』の「殺し場」のト書など、その演出は詳細で深刻です。寛政二年切首に似顔を用い、寛政三年には舞台で顔を洗い落とす趣向が大当たり、寛政六年、顔とかつらの仕掛けを始めるなど、また京伝の黄表紙『世上洒落見絵図』(寛政三年刊)に「舞台で役者のうちをその僅正写しにして見せれば大入りにて羽目をはずす」とあることにより、「正写し」というリアルさが世人の歓迎を受けた時代でした。
このリアリズムの風潮は、浮世絵においてもすでに役者似顔絵として発展してきていました。役者の世界でも、それぞれ立ち役・女形・道化などと役者の個性に応じた役柄が固定し、脚本に一定の基準ができ、筋や内容には変化をもたせてはいますが、形式が一定化し、世界の立て方によって自ら拘束されることになりました。したがってそのなかでは、脚本より役者各人の芸を生かす工夫に自由さがあり、観客は役者個人を最贋にして、その個性ある演技に喝采をおくったのでした。このような事情から浮世絵の役者絵においても、ただ紋所のみを明記するものでは満足できず、似顔の役者絵が要求されるようになってきました。すでに鳥居派は歌舞伎界と結託し、清信以来の伝統を墨守し、形式的にも類型化をまぬかれずにいましたが、肉筆では宝暦頃より、版画においては、錦絵誕生の機縁となった絵暦から始まるといいますが、鳥居派以外の写実主義による個性描写に新生面を開拓したのは、一筆斎文調と勝川春章です。特に春章は絵本『役者夏の富士』(安永九年)を描き、役者の平常生活を素顔によって紹介したのです。これは現代における俳優の私生活を書きたてる週刊誌と同様な役目を果たし、役者に対する大衆の人気が、必然的に要望したものといえましょう。また楽屋における役者を描いたり、舞台上で活躍する姿に個性と役柄を明らかに写し出し、躍動美と型式美とを十二分に盛り入れたういういしい作品を描き上げることに成功しました。役者絵に大判を使用した清長は、役者のみでなく出語りをも画面に描き、さらに勝川派の春潮、春好、春英など次々とこの似顔役者絵路線を拡大強化し、客観的写実をひときわ徹底させるため、顔面の拡大描写を行い、ここに似顔絵の究極の姿として大首絵が誕生することとなりました。このような役者絵の発展上に、役者の個性と演ずる役柄とが互にとけあって、ヴィヴィッドな写実の上に最高のハーモニーを表出した写楽が登場するのです。
このような寛政期における歌舞伎界と浮世絵界の写実的手法はともに美しく開花し、当時の大衆の要求に十分こたえうるものになっていきました。写楽の後には、大衆の嗜好を完全にとらえ、そして大衆に迎合し、一世を風扉した豊国が出現します。一方歌舞伎界では、化政期を迎えますと、四代鶴屋南北(1755年-1829年)によって当時の大衆の好みを端的に取り入れた生世話狂言がつくられ、歌舞伎界の隆盛期を現出するのです。
寛政歌舞伎は前述のごとき、天明歌舞伎と化政歌舞伎の谷間であり、経済面にも不振をきたしてはいましたが、この危機をのがれることのできた一つの大きな理由に、文運東遷という時代の波にのり、狂言作者の並木五瓶が江戸へ下ってきたことをあげることができます。写楽は東下したばかりの五瓶の作品を矢継ぎ早に五作品も描きつづけました。五瓶と写楽の関係は、なんらかの有機的関係がなければ、このような現象は起こりえないと考えてもよいのではないでしょうか。
並木五瓶は延享四年(1747年)大阪道修町に生まれ、明和六年頃すでに浜芝居をつとめ、市山富三郎(のちの三代瀬川菊之丞)の座作者として認められ、安永六年角座の立作者となり、『金門五三桐』ほかの傑作を世に送りました。加うるに天明期にはいって、先輩格の中古歌舞伎作者の祖といわれた奈河亀輔が劇界から消えますと、地位技倆とも京阪第一位の声望をあつめることができました。この五瓶と、江戸に生まれ、初舞台も江戸であった三代沢村宗十郎が初めて一座したのは、安永三年(1774年)十一月京都の藤川山吾座でした。翌年十一月の宗十郎の大阪の初出演(中の芝居三桝松之丞座)も両人は一座しています。このような二十代の二人の出会いは、お互いに親しさを増していったようです。宗十郎も安永六年十一月江戸へ帰り、江戸における和事師としての名声と地位を確立し、その道の第一人者といわれるようになっていきました。寛政三年(1791年)11月、95年ぷりに大阪へ行った宗十郎は、五瓶と京阪の劇界で再度親交を深めることになりました。このような経過をもった両人の間で、五瓶江戸誘致の話が出て、『戯財録』にいう「江戸へ三百両にて行く」という狂言作者としては前例のない高額給与をもって五瓶東下りが実現することになったのです。
五瓶が江戸にきて、自作を初めて上演したのは、寛政六年十一月顔見世狂言の『閏訥子名歌誉』でした。次いで閏十一月には『花都 廓縄張』を上演しました。しかし江戸人の上方作者に対する拒否反応が極度に表面化し、まったくの不評をこうむってしまったのです。つづいて寛政七年正月には『江戸砂子慶曾我』と『五大力恋絨』の作を書き上演しました。写楽はこれらの作をことごとく取材して作画しています。当時好評を得ることのできなかった五瓶の作品をこれほどまでに描きつづけた写楽には何か理由があってしかるべきでしょう。『五大力恋絨』がきわめて写生的描写に演出されている作品であることからすれば、五瓶のそのような作劇態度が、写楽の鋭い対象観照の精神と著しい近似性を見出したためか、また上方人としての五瓶に対する親密感が先行したのではないかとも想像できます。それをさらに拡大すれば写楽の上方出身説にもむすびつくかもしれません。しかしこれからの総合的な研究にまたねばならないところです。
最後に写楽の出現は、寛政期という歌舞伎界が経済的に困窮し江戸三座とも控え櫓で興行した時代で、しかも天明から化政期の隆盛期の谷間にある空隙時代であったればこそ、あのきわめて個性的な作風の写楽が誕生しえたのではないかと考えるわけです。
写楽の作品の分類
写楽作品の年代考証は、多くの困難をともないつつも時代の経過によって次第にその全貌が明らかになってきました。写楽画の制作期間について、タルトがまず初めて発表したところによれば、天明七年(1787年)から寛政七年(1795年)にいたる前後九年もの長年月であると指摘しました。その後研究がすすみ、井上和雄氏は寛政六年(1794年)春から翌七年五月までの十七ヶ月であると短期間説を主調。さらに研究を深めたヘンダーソンとレデュの両氏は十ヶ月作画期説を見事に限定しました。
元来役者絵はそこに描かれている人物の衣紋により役者名がわかり、舞台上の姿態からその芝居の外題が判明、さらにその両者から該当芝居の上演年月なども知ることができます。当時の紋番付と絵本番付や歌舞伎年表など、これらの検索には考古の資料といえましょう。これらの調査によって多くの研究家は、写楽の作画期を丹念に調べ、いろいろな変遷を経つつも、現在寛政六年五月に始まり、七年正月に終わる全十ヶ月(なかに閏十一月がありますので)の作画期こそ、写楽の役者絵から推定する確実な日限であると考証されています。部分的な役名考証には、まだ異説があるとはいえ、取材諸狂言とその上演劇場も含めてすでに動かし難いものになっています。そしてこの役者絵と他の若干の相撲絵・武者絵その他をまじえて四期にわたる写楽作品の分類が行われた。これはヘンダーソン、レデュ、吉田の三者が諸種の交渉結果を中心に、画風の様式変遷を加えたものです。以下年代順に変遷の過程における特色をおのおのみてゆくことにしましょう。
第一期 寛政六年五月の三座の狂言を描きます。
『花菖蒲文禄曾我』(都座)―十一枚i、『佐々木岸柳 志賀大七 敵討ち乗合話』・浄瑠璃『花菖蒲思 算』(桐座)-七枚-、『恋女房染分手綱』・切狂言『義経千本桜』(河原崎座)J十枚i 全二十八枚は、みな大判型式、半身像、バご楽画」の落款です。黒雲母の鏡面に描き出された上半身は、顔面の印象をきわめて強く打ち出し、描線を省略に省略を重ねた上に、配色の単純さでさらに効果を盛り上げています。全作品中最も優秀な芸術性の高い粒よりの作品群で、写楽の技巧の秀抜さと役者の的確な演技のとらえ方に注目できるものです。この最初の大首絵はさすが人の目を驚かせるのに十分であったとみえ、なかなかの売れ行きであったようで、一画の後摺りのものや、色がわりが数種みうけられます。また版画の最少の色彩数で最高の効果を上げる特色を十二分に発揮し、この第一期の作品のみで優に世界の写楽の名を冠たらしめています。
第二期 寛政六年七月の二座と同八月の一座の狂言を描きます。
七月狂言『傾城三本傘』(都座)-十六枚-、二本松陸奥生長』・浄瑠瑠『桂川月田心出』(河原崎座)-十枚- 八月狂言『神霊矢口渡』・『四方錦故郷旅路』・浄瑠瑠『月眉恋最中』-十一枚- このほかに『都座口上図』一枚が第二期の冒頭におかれます。
全三十八枚に及ぶこの第二期の作品は、まず大判形式-八枚―と細判形式―三十枚-のサイズに分かれます。大判形式のうち七枚は二人立ちの全身像で、他の一枚が写楽役者絵における大判形式中唯一の″一人全身像”の「都座口上図」であり、これもふくめて第二期大判形式のものは、全部全身像といえます。また、バご雲母摺りII『月眉恋最中』における梅川と忠兵衛の死出の旅路に立つ二人を描いた作品のほかは、全部淡紅色の雲母摺りであります。
細判形式は、全部一人立ちの作品であり、夜の舞台面を表す二枚の作品(「二代大谷鬼次の川島治部五郎」と「市川男女蔵の富田兵太郎」が鼠地であるのを除けば、他の二十八枚はみな黄潰しの作品です。落款は大判・細判ともに「東洲斎寫巣画」。
大判形式の画面をみますと、描写に一段と余裕ができ、のびのびとした構成のもとに芝居のストーリーを二人の人物のからみあいのもとに自然と語りかけ、言外の情をゆくりなくも表現しています。舞台の情緒を、役者の表情を、動作の美しさをあますところなく見事に表出しています。細判のものは、大判に比較してやや堅い画面構成ではありますが、特に組み物の連続描写に卓越した力量は注目すべきで、三期以降の細判作品と比較するとき、やはり秀逸さを誇っています。写楽細判の優作はこの期に集まっており、写楽芸術の一つの進展を意味していると解することができます。
第三期 寛政六年十一月の三座と閏十一月の一座の狂言を描きます。
ほかに十一月場所を描いた相撲絵、土俵入りの一枚と三枚続き四枚と二代市川門之助の追善絵二枚がこの期の作品に組み入れられます。
全六十三枚。このなかで「七代片岡仁左衛門の紀の名虎」の細さんVいI、わむらそうじゅうろうくじや≪*ii410う絵一枚は、三代沢村宗十郎の孔雀三郎」と組み物になるのですが、背景の竹藪を示す点描が、後者の上部から下部にはねているのに対し、前者は下部から上部にはねていて、その上顔面描写やポーズのつくり方に疑問点がもたれ、現在所在不明のためその作品自体に接する機会もなく確言はできかねますが、一応参考図版に入れて除外しておきました。
この期にはいって写楽の画風は著しく硬化の道をたどり、芸術的香りも次第に色あせ、作品価値が低下してきています。版形式は、細判四十六枚、間判十四枚、大判三枚という内訳になっています。細判役者絵には、パックのない黄潰しのものもありますが、多くは背景に樹木の一部や舞台背景を描きそえたものが出てくるのが特色の一つです。役者の表情美から、動作を一瞬キャッチするポーズの美へと移行した写楽の着目が、さらに進んで舞台を背景に立つ役者の総合の美へと変化していったことを示すものといえましょう。しかしこの期の写楽作品にみられる一般的停滞状態からして、細判のなかに息づく役者の動きは一段と鈍重となり、背景と役者との分散した美の不調を露骨に呈し始めました。これは写楽の特色がますますうすれて陳腐な表現に墜していった芸術性の低下を判然とみるものに覚えさせます。役者の全描写を、その顔面表情と型のすっきりきまった姿態形成とによって、昇華した純粋の美をみせた写楽特有の美観はすでに頂点をこえ、その低調化の拡大が始まってしまったのです。
間判作品のうち十一枚は、黄地半身像で第一期の半身像形式が復活しています。しかし第一期と比較してみますと、これらの第三期作品はあまりにも格差が激しく、画面からはみだすような自由な構成と迫真の気晩にみちた第一期作品とは異なり、画品の乏しさを明白に露呈しています。この十一枚の画面には、それぞれの役者の替紋と屋号俳名が記されています。他の二枚の間判作品は全身像で、寛政六年十月になくなった門之助追善絵であり、役者絵の間判作品は第三期に全部網羅されています。これらの間判をシリーズと認め、配り物とみるむきが強いです。
大判作品は三枚続きの相撲絵。ここでも細判作品に初めて現れた続き物がみられ、しかも背景が描かれています。写楽の相撲絵として処女作ということになりますが、写楽ならではの見事な作風を示しています。
特に大童山文五郎の似顔はよく対象を把握して秀逸な描写となっています。
次にこの第三期の落款ですが、細判六枚が「束洲斎寫楽画」とあり、ほかはみな「寫巣画」になっていて、斎号の取れた落款が用いられています。斎号のある落款は第二期から第三期への過渡的作品であることを示しているといえましょうが、なぜ斎号を取ったか、また、なぜ急速に写楽芸術が第三期にはいり下降線をたどりだしたか、背景の力を借り出さなければまとまらないほどの創造力の枯渇をなぜ表わさなければなりませんでしたか。十一月狂言だけで五十四枚という全作品の三分の一強の多作品をI挙につくったという、板元の濫作強要による芸術的良心の低下によるものでしょうか。多くの問題点を抱えているのが、この第三期の作品群です。
第四期 寛政七年正月の二座の狂言を描きます。
『再魁霖曾我』(桐座)-三枚-、『江戸砂子慶曾我』・『五大力恋絨』(都座)―七枚-。このほかに相撲絵-一枚-と武者絵-二枚-、恵比寿-一枚―がこの期の作品に組み入れられます。
第四期の作品は第三期よりさらに画格の低下がみられ、写楽の廃筆も無理からぬと思われるほどです。芸術的香りの消えうせたこの期の作品は、写楽の終焉を感じさせるのに十分です。落款はもはや斎号のあるものは一枚も見出すことはできず、「寫巣画」のみに終始します。
このほかに写楽描くといわれる、版下絵と肉筆若干が存在します。特に九枚の相撲版下絵は故小林文七所蔵であり、大正十二年の関東大震災で烏有に帰したものです。また、もとフランスのバルブートの蔵品であって、現在アメリカのボストン美術館に二枚、シカゴ美術館に一枚(これは昭和四十八年「シカゴ美術館展」でリッカー美術館に陳列された)、フランスのギメ美術館に二枚おのおの所蔵されている五枚とほかに四枚の役者版下絵計九枚が知られています。この相撲絵と役者絵の版下絵は、種々の点において疑問をもたれています。特に描かれている力士と役者の考証からくる疑問が主であり、その上に落款にも疑いがもたれて、偽筆としての見方が非常に濃厚です。
シカゴ美術館蔵の扇面「お多福」は、昭和四十七年に開催された「在外浮世絵名作展」で、銀座松坂屋会場に陳列されました。従来肉筆画ともいわれてきたこの作品は、線と文字と落款とが木版で、着色だけは手彩であると述べているヘンダーソンの説もあり、色々の角度からこの作品を実際手に取って検討考察した結果、「合羽摺」にほぼ間違いないということになりました。しかし制作技法の面はこれで解決されたとしても、それが写楽の作品であるということには未だ確定しかねる点が多々あり、今後のさらに進んだ研究をまたねばならない現状です。
江戸時代の写楽批価
現在知られている写楽作品を、絵本番付、辻番付、紋番付、歌舞伎年表などを対照にして考察を加えますと、寛政六年五月から翌七年正月までの十ヶ月という短期間の制作になることは、前項の写楽作品の分類でみてきたところですが、この短期の作画は、きわめて特色あるものとして、その初期のものが世上に流布されたときは好評を博したでしょう。それは初期の大判作品の残存数が最も大きく、異版もかなりみられるからです。このような出発点の殷賑さにくらべて、急激に衰退をむかえたのも事実で、世界に一点しか見出されないものも、作画期の後半期になってからのものに多いことで判然とします。
しかしこのような事情にある写楽版画に対する客観的な記載は、これまた極少数で、寛政期に写楽について多少ともふれた資料を列記すると次の四つに限定されてしまいます。
一、十返舎一九画作の黄表紙『初登山手習方帖』の挿絵
二、式亭三馬画作の黄表紙『稗史億説年代記』の挿絵
三、栄松斎長喜の錦絵「高島屋おひさ」
四、大田南畝原撰・笹屋邦教補の『浮世絵類考』の記載
以下簡単な考察を各項について加えてみましょう。
一、この黄表紙は写楽の作画期より一年後の寛政八年に出版されたもので、問題の挿絵は、その七、八丁にわたって見られる大きな絵凧です。
それには市川暇蔵と思われる暫が「東洲斎寫巣画」の落款で描かれています。残念なことにはこの絵凧の周辺に書かれている戯文は、この絵にまったく関係なく、そこに描かれている因果関係を知りたくも何ら手掛かりを残しておいてはくれません。しかしこの黄表紙の作者一九は写楽とはまんざら無関係ではありません。大阪の材木商の女婿となったことのある一九は寛政六年の秋、ちょうど写楽の作画しているときに、通油町地本問屋蔦屋重三郎の食客に落ち着き、錦絵に使用する春水を引く務めをしていたといいます。
写楽の版画はこの板元蔦屋重三郎のみの出版であるところからすれば、一九とはもちろん顔見知りであったと考えても無理はなさそうです。これにもう一つ、この黄表紙には大阪の画家で狂画に妙を得て、安永から享和(1772年-1803年)にかけて活躍した耳鳥斎のものがあります。故宮武外骨氏は写楽のことを耳鳥斎のごとく一種瓢軽な似顔絵を描いた人であると評しています。この役者絵を描く耳鳥斎と大阪で浄瑠瑠を作っていた一九はともに上方で会う機会は当然あったでしょうし、この関係に写楽が加わるとなると非常に興味深いことになります。写楽は前々項で述べたごとく上方出身の五瓶と関係のあることも考えられ、写楽・五瓶・耳鳥斎・一九の四人の関係において上方という地域が浮かび上がってくるのは否定できません。
二、享和二年(1802年)刊行のもので、写楽の作画期より七年後の黄表紙です。問題になるのは、その中に描かれている「倭画巧名沓」と題した地図様の挿絵で、真中の大きな島にはむかし絵-菱川吉兵衛・石川豊信・奥村重長・鈴木春信・冨川吟雪・房信・一筆斎文調・磯田湖竜斎・春町を描き、古川三蝶と栄松斎長喜をこれに接近した島に描きます。さらに上方に一島に一名を記載するのは、歌麿・北斎・写楽の三人で、この三大浮世絵師が独自の立場に立っていることを示しているようです。このように写楽の作画期が終わったあと七年後に、歌麿・北斎などと同様な立場を写楽に与えていたということは無視できないでありましょう。
三、この錦絵は、ポッパー氏旧蔵の一枚で現在所在不明の作品。この錦絵の立ち姿の美人が持つ団扇絵が問題で、そこに写楽が描く「四代松本幸四郎の山谷の肴屋五郎兵衛」の鉢巻をして煙管を持つ姿が描かれています。写楽の作品と実際に異なる点は左右反対に描かれていること、蔦重の板元印と写楽の落款がないことで、この錦絵によって理解できるのは、写楽の普及度が案外高かったのではないかと思われることです。なお写楽問題で注目される錦絵に享和三年歌麿作の「お半長右衛門」があり、そこで「わるくせをにせたる似つら絵」ではなく美化して描くのが歌麿の本領であるといっています。これは明らかに写楽を意識しての語に相違ありません。
享和三年といえば。写楽作画期よりすでに八年を経過した時点でも歌麿は写楽を引き合いに出すほど意識していたのでしょうか。考えてみれば蔦屋重三郎一軒の板元で最後までつらぬいた写楽は、何らかの意味において特別な関係をもっていたはずです。その上最初の作品から雲母摺りで大判の版画としては最も金のかかる作品をつくらせたのです。この事実は一般の浮世絵師としては超破格であり、普通は初め黄表紙の挿絵をかかせ、実力が認められれば次に一枚絵をかかさせてもらい、雲母摺りの作品など初めから手掛けるなど思いもよらないことでした。無名時代蔦重にひろわれ、このような経過をふみ一流絵師になった歌麿は、写楽作品の出版に打ち込んだであろう蔦重の姿をみて、女絵画家と役者絵画家との違いをのりこえて、大いに嫉妬もし、強い対抗意識をもったと考えられます。
四、『浮世絵類考』は、寛政初年大田南畝が原撰し、寛政十二年に南畝はこれに笹屋邦教のかいた『古今大和絵始系』をのせ、この時点で写楽の記事が浮世絵類考に記載されたと考えられます。
さてその後、『浮世絵類考』の写楽の項が江戸時代にいかに補充されてきたかを年代順に並べてみると左のごとくになります。
寛政初年(1789以降)『浮世絵類考』(南畝原撰)
寛政三年(1791)『仕懸文庫』で京伝手鎖五十日、蔦重身上半減の処分受ける
寛政六~七年(1794~5)写楽作画期
寛政八年(1796)『初登山手習方帖』の絵凧(一九):長喜の「高島屋おひさ」この頃
寛政九年(1797)蔦屋重三郎没す
寛政十二年(1800)『浮世絵類考』に笹屋邦教、付録始系を補す
享和二年(1802)『稗史億説年代記』の挿図(三馬)
享和二年(1802)『浮世絵類考』に京伝追考をなす
享和三年(1803)歌麿「お半長右衛門」を描きます
文化十二年(1815)『浮世絵類考』に曳尾庵補記す
文政元~94年(1818~21)『浮世絵類考』に三馬補記す
天保四年(1833)『尤名翁随筆』(英泉編)-『続浮世絵類考』
天保十五年(1844)斎藤月岑さらに補記す-『増補浮世絵類考』
文久三年(1862)三代豊国、写楽作品の模倣版画つくる
慶応三年(1867)関根只誠筆写す
慶応四年(1868)川崎千虎書入れ竜田舎秋綿編序-『新増補浮世絵類考』
ここで浮世絵類考の写楽に関する記載を検討してみますと、南畝・京伝など当時のインテリ文人にあまり好感がもたれていなく、新進の若い三馬などが『稗史億説年代記』で写楽を一流絵師に見立てているのは対照的です。この冷たいとも考えられる写楽批判は写楽を五瓶と同じ上方出身とみれぱ、一応の理由が成り立つが、断定はできかねます。
文化十二年曳尾庵の「筆力雅趣ありて賞すへし」と写楽を讃えているのは、時代の経過とともに、当時の偏見的事情に左右されない正しい評価が表れてきたといえましょう。文久三年には、三代豊国が写楽作品の模倣版画をつくるなど、天保以降幕末にかけて一般に写楽の認識が固定してきたことが、浮世絵類考記載の内容の変化にも見受けられます。
写楽別人説
『稗史億説年代記』の三馬補記に、初めて写楽が江戸八丁堀に住んでいたことを述べ、さらに斎藤月岑は写楽は斎藤十郎兵衛であり、阿波侯の能役者であると記した⑥。この月岑の記載は、他に資料がまったくないという写楽研究では、その後金科玉条となってしまいました。
明治四十三年、ドイツ人ユリウスータルト著の『写楽』がミュンヘンで出版されたのが写楽研究の嘴矢といえましょう。一般版画の複製が、明治十八年頃吉田金兵衛の手によってつくられ、これは真物として外国へ売り出されたとも伝えられるもので、相当優秀なものでした。現在大英博物館に所蔵される写楽二十七点は、明治三十三年に離日したアーネストーサトウのコレクションであり、海外流出の浮世絵版画はおびただしい量にのぼったのです。このような西欧におけS浮世絵事情を背景に写楽研究がまず海外で発表されたわけです。タルトは能役者説にたくましい想像を付与し、「蜂須賀城を蔽ふ松や杉の影のした、徳島の神社の霊地内仮面を着た役者にまじつて、自分も奇怪な仮面を附け、古い崇高な劇的芸術の幽玄な伝統的空気に取り巻かれ、写楽は神聖な能劇の舞台を歩む」と記します。
大正期になり、このタルトの写楽研究に刺激されて、日本の研究家では中井宗太郎・橋口五葉・野口米次郎・藤懸静也・仲田勝之助の諸氏が写楽に対する論稿を発表しました。この間大正十一年邦枝完二が『地獄へ落ちた写楽』という脚本をかき、孟蘭盆の仏事の帰りがけ、聖堂の裏で大事な右手首から先を、モデルにされた歌舞伎役者のやとった浪人者に斬り落とされる写楽は江戸八丁堀の阿波屋敷に住む能役者になっています。
この写楽すなわち斎藤十郎兵衛説に異を説えたのが鳥居竜蔵氏で、大正十四年のことです。同氏は、写楽の姓名は春藤次左衛門が正しく、春藤派の能役者で藩主に重用された身分であるとしました。しかしこの論は再転して後に斎藤説に変わりましたが、写楽が能役者であることには変わりはありませんでした。その後能役者説をとなえた人々(研究家・小説家その他の発表したもの)を年代順に述べてみますと、鳥居氏のあとでは邦枝完二(昭和四年)、三谷松悦(昭和十二年)、横川毅一郎(昭和三十一年)、松本清張(昭和三十二年)、今東光(昭和三十三年)、小野忠重(昭和三十九年)、横倉辰次(昭和四十年)、小田仁三郎(昭和四十年)などがあります。写楽すなわち能役者のほかには、アマ絵師(野口米次郎)、貴人(森清太郎)、鳥居清政(溝口康麿)、北斎(由良哲次)、司馬江漢・長喜(福富太郎)、豊国(石沢英太郎)、蔦重(榎本雄斎)、円山応挙(田口仰三郎)、谷文晃(池上浩山人)、酒井抱一 (向井信夫)、谷素外(酒井藤吉)、蒔絵師飯塚桃葉(中村正義)、面つくり(西村亮太郎)、能面師(大岡信)などがあり(榎本雄斎氏の調べによる)、まさに驚嘆に価する多様性がここに見出されます。
写楽すなわち能役者説が天保末期の『増補浮世絵類考』から始まり、現在に至る一世紀あまりの間、浮世絵界の一論拠となって経過してきましたが、初めからのこの説の論拠を探し求めても、何らそこには史実性がなく、幻の写楽を追いかけていたことになります。たしかに斎藤十郎兵衛は史上実在の人物ではありますが、これと写楽を結びつけるのは現在の進んだ研究では無理になってきました。昨年近藤喜博氏は、大阪天満板橋町に住む「片山なみ」なる女性が写楽と名乗る人物の妻であることを「白川家門人帳」を根拠として述べ、写楽の上方出身説に一論を添えることになりました。資料の乏しいがためとはいえ、飛躍した論理を組み立てるのは極力さけねばなりません。写楽は写楽その人であって、写楽以外の別人を当てるのは、現段階の研究成果としては無理のようです。写楽問題は振り出しにもどってしまうことにはなりますが、多くの人々の写楽別人説は決して写楽研究の上に無駄であったわけではありません。
写楽作品の参加
このような写楽研究の遅々とした歩みにもかかわらず、写楽芸術の評価はきわめて高大です。十七世紀スペイン最大の画家で、フランドルの写実主義を十分に摂取、空気遠近法、明暗描法、光線の表現などに従来みられなかった完成の域に達し、心理学者のように人間を描くとまでいわれた、ヨーロッパ絵画史上最もすぐれた肖像画の名手ベラスケス、そして十七世紀オランダのすべてであり、明暗の対照の激しさのなかに対象を徹底的に写実に描き、表面的な美しさや類似よりも、人間の心の深さを描こうとした巨匠レンブラント、この卓絶した二人に並ぶ肖像画家と写楽はみなされ、その国際的評価はすこぶる高いのが現状です。写楽芸術の発見は、ドイツ人タルトの『写楽』によって始まります。彼は思想にふける人、すなわちエディプスです。彼は冒険的に、人間の顔からわずかに現れる熱情のスピンクスに接近しようとします。単に軽蔑されるばかりでなく法律の権利さへ奪われている一階段、馬鹿げた相撲取りと同程度に置かれた一階段、赤の絵具を顔に塗って恐ろしい武者となり、死人のように蒼白な白粉を塗って女に扮し、そうして愚な民衆の賞讃を博そうとする溝臭い傲慢な虚栄心をかくすことが出来ない野卑な一階段を見下しました。所で写楽が画家として、必ずや無慈悲な薦刺家とならねばならぬと私共は予期するでしょう。
このタルトの写楽に対する批評は、多くの写楽礼讃者をつくりましたが、辛辣な餌剌家としての、写楽に対するイメージは、その作品分析にも基調となっていきました。このタルトの写楽讃美に始まり、現在にいたるまで、種々の違った角度より、いろいろの人々が写楽を謳歌しています。
画家でありそして歌舞伎と浮世絵にユニークな評論をかいた岸田劉生氏は、写楽の画風はユーモリストであり、戯作家的であり、また厳正なる写実家であったと次のように述べている(『浮世絵板画の画工たち』昭和四年)。
写楽の似顔は、より認識的であり、より観照的であり、より辛辣であり、より深刻です。写楽は浮世絵における戯曲的要素を非常に多くその内にもち合わせた画家であると見るのが当を得ていると思います。浮世絵は、その質が本道の美術とは反対のものであって、卑近、狼雑、現実感、遊戯、戯作家、そういう素質をもって生成されています。ところが写楽にはこの狼雑、遊戯という感じが、むろんあるにはありますが、露骨に、表面的な主題としてはなく、この戯曲的要素が特に目立ってみえます。すなわち、日本における、カリカツールの唯一の天才といっても過言ではないのです。実に彼の肖像は深刻なカリカツールです。しかも、決して単にふざけたものではなく、かなり深い自然観照と、絵画的知識とをもって描かれてあります。その顔は肖像画としても立派に生きていて、へんに生々しく、深い写実味があふれています。
歌舞伎研究家であり、そして浮世絵にも造詣が深かった吉田喚二氏は、単なる写実の名手でなく、そこには浪漫的、理想主義的な発想を考慮しなければならないといっている(『東洲斎写楽』昭和十八年)。写楽の絵は、優艶美を描かうとする客観的な目的はなく、其処に生み出されたものが優艶であらうがなからうが、彼は自己の描かんとするものを素直に描いてゐるのです。写楽は自己の憧れを描いてそれが彼の「真」であったと伝えるのです。彼の絵には写すのでなしに、描く、と伝える意志があるのです。そこが他の似顔絵画家と異なるところなのです。殊に、彼の絵は、単に役者を描いたのみですが、それは、その役者の芸風性格に及び、役者が作りなす舞台の雰囲気に及び、更に「歌舞伎」そのものまでも描き得ているのです。これ程迄に打ちひろがる内容を、単なる客観的写真によってのみよくなし得るとは考えられない。そこには、彼の描写意慾の旺勢さと、それを芸術に醸し出す強靭な芸力があったからです。
最後にアメリカ人マニー・L・ヒックマン氏の評判を聞いてみましょう。(『在外秘宝 東洲斎写楽』昭和四十七年)写楽の芸術的重要性は、人物描写の際立った才能だけからは説明できません。むしろ彼の業績は、「総合的な」芸術作品の実現、大きな力と独創性を基本的に組み立て、構成的に配置した構図にあります。このようにして彼の最上の作品は常にある微妙な構成上の力点-緊張、均衡、色彩並置-といったものを第一義としています。そしてこのような芸術的考慮が身体的、心理的特徴を描写する興味に常に先行しているという事実は彼の特質の一端を物語っています。つまり、彼の第一義としたものは、絵画的ルポルタージュではなく、すべての偉大な芸術家に共通の関心、すなわち、芸術作品として固有な価値をもった、動的で、絵画的イメージの創造だったのです。
時代の移りとともに写楽芸術の評価にも以上の諸文を参照すればかなりの変化があることは諒解できるでしょう。「写楽讃」の内容にしても明治末年のクルトとヒックマン(昭和四十七年)の論には近代的メスの入れ方で全く斬新さを示しています。これらに一貫しているのは何よりも写楽への傾倒であり、彼の比類ない芸術性への讃歌です。のびのびと走る描線、簡潔な色面配置、大胆な形態把握、意表をつく構図、理想的な様式美を追う安易性からの離別、どれをみても心憎い芸術表現です。
江戸時代の芝居は、一日の慰みを見物に与え、封建社会制度下における大衆に、非日常の世へ陶酔させることが可能でした。しかしこれを可能にさせるには、観客が求めている適当な新しさを絶えず加えた演技なり、狂言内容を披露しなければなりませんでした。大衆は飽きやすく、移ろいやすいものでした。ともに庶民を対象とする浮世絵の世界においても同様で、北斎がオランダ仕込みによって水平線を曲線で描くなど新奇な趣向をみせたのも購買者に対する一つのサービスともいえましょう。その新奇な趣向は絶えず対象となる人々に歩をあわせ、現代でいうアバンギャルドであっては決してならなかったのです。
しかし写楽の絵はまさに当時の「前衛」でした。従来娯楽性を基底において制作された役者絵は、客観的描写による美化された画面にこそその意義を求められ、ブロマイドとしての用途を果たすことができたのです。しかるに写楽の絵は、この基本主張を無惨にもたたきこわしました。このような写楽のいき方が異例であり、従来の役者絵にとって異質であったことは否定できません。この異例さは作風のみでなく、色々な点で写楽に見出すことができます。
一、初作品から雲母摺りを使う豪華作品がみえること。
二、出版元が蔦屋重三郎一軒に限られていること。
三、作品の優秀なものが最初にきて、漸次芸術性が低下すること。
四、伝記がまったく不明なこと。
以上他の有名浮世絵師ならば考えられぬ事項です。写楽を讃し、写楽を世界的作家にしても、その周辺は今もって空洞となっています。同時代に生きた人々とつながりをもてないこの孤独な写楽に一日も早く血をかよわせ、歴史的な背景のもとに讃美することができるのを祈るのみです。
地方版画について
徳川時代幕府の政権所在地であった江戸は、政治・経済・文化あらゆる面の中心地であり、指導的立場をとっていました。しかし封建治下の諸侯が各地に割拠して、大諸侯の城下には、おのおの独特な文化・芸術をも発生するいたり、地方文化の殷盛は、近世における一大特色となりました。
このような一般情勢は、江戸時代の絵画界でも新しい世界を開拓し、版画の分野においても、その著しい例をみることができ&・近世芸術を起こした京都大阪は、長い年月にわたり文化の中心地であったため、貴族的な高踏芸術を鑑賞するに急で、本当の意味での庶民芸術は育ちにくかったです。
版画そのものは複数芸術で、安価にして商品価値を生み出すための作品であったため、江戸では版画を新芸術として鑑賞しましたが、京都大阪ではこれを軽視する傾向が強かったです。一枚絵としての版画の利用度より、版本として絵本や名所図会などに多く活用されました。
このため江戸の版画界がリーダーシップを取ることになり、江戸以外の地に生まれる版画様式に影響をもたらすこととなるのです。たとえば名古屋においては葛飾北斎が来遊し、門人牧墨僊の家に滞在したため、北斎の系統の画人が多く輩出、『北斎漫画』の初編なども墨僊宅で描いたことは有名です。このほか金沢・仙台・徳島などにおいても版画を制作したといわれ、主として摺り物が多く、数度の色摺り版画でした。
さらに現在数百の遺存作品をもつ地方版画として名のあるものに長崎絵と富山版画があります。この両者と京都大阪の上方絵は、江戸の版画界に準じて、地方版画のベストースリーで歴史的変遷も明らかにされ、内容的にも興味深いものがあります。長崎絵は日本版画のなかで外国人を取り扱った点で東の横浜絵と並ぶ異色の作品群であり、富山版画は越中富山の薬行商の宣伝用に作られ、顧客の土産のために制作されたものが多いため、芸術的にみるべきものは概して少ないです。この上方・長崎・富山の版画はその初期には各地特有なムードをもつ版画でしたが、時代の経過に従い、江戸絵の影響を受け、漸次その特色もうすらいでしまいました。
長崎絵
天文十二年(1543年ポルトガル船が大隅の種子島に漂着し、領主種子島時尭は鉄砲二挺を譲り受け、西欧との交渉が始まりましたが、これより二十四年後の永禄十年(1567年)肥前大村の領主大村純忠は、当時深江村と呼んでいた一漁村を長崎と改名、ここに教会堂を建て、南蛮貿易・吉利支丹宗門の拠点とし、以来、南蛮・唐船の来往する新開港として栄えました。しかし三代徳川将軍家光の時代となり、吉利支丹の処刑が次々と行われ、寛永六年(1629年)七月長崎で拷問による多数の改宗者がでて、この年から長崎で踏み絵の制が始まったといいます。寛永十一年五月長崎に出島を築き、93年五月出島にポルトガル人を移住させます。翌年十月島原の乱が起こり、ついに十六年七月ポルトガル人の来航を禁じ、98年平戸のオランダ商館を長崎出島に移し、鎖国が完成するのです。かくて以後オランダや中国に限って交易を許し、いわゆるポルトガル・スペインが代表する南蛮文化にかわり、オランダを主とした紅毛文化が中国文化とともに日本に流入してくることとなります。そして長崎には、洋画系の南蛮絵という初期洋画や江戸中期以降の紅毛絵とともに、北画・南画と洋風画の影響を受けた沈南殯派の中国系統の絵画もありました。その間にあって庶民的感覚のあふれた長崎版画が存在したのです。出島は総坪数三千九百七十の埋め立て地で、扇形になっているために扇島といいました。周囲は高い板塀をめぐらし、そこへの出入を許可されたのは丸山寄合町の遊女と高野聖だけでした。この出島にあるオランダ屋敷とならんで唐人屋敷がありました。唐人すなわち中国の商人が来港してきて、寛永十二年(1635年)以降オランダと同じく長崎に限って貿易を許され、日本人と雑居していましたが、い私いろな弊害が生じたため、元禄元年(1688年)長崎郊外の十善寺村に約九千三百坪の居留地をつくり、唐人屋敷をつくりました。このオランダと唐人の屋敷は、鎖国下の日本にあって、91つの外国に通ずる明かり窓となりました。この狭小な窓からみた異国の文物は外国への興味や関心を深め、それが長崎に対するあこがれとなり、そのまま版画に制作されました。この長崎で旅人相手のお土産絵として制作された版画を長崎絵と呼称し、そのエキソチごzな内容を紹介しました。
長崎における版画の嘴矢は、正保二年(1645年)版行の「万国総図人物図」(二枚折屏風仕立て)で、「万国総図」は肉筆画ですが、「人物図」は墨摺りの上にテンペラ(顔料ににかわや糊などを混ぜた水彩絵具)で筆彩しています。木版摺りの世界の地図や人物が長崎で十七世紀の半ば頃より制作されましたが、この絵は、後の長崎絵とはいちじるしく趣を異にしていました。長崎絵はまず題材に特色があります。江戸の錦絵は、美人・役者・風景という三大テーマをもって描かれていますが、役者絵は皆無で、美人画と風景画が若干存在します。特に美人画は紅毛と唐人が大多数で、なかに日本の遊女を描くこともありますが、このときは必ず蘭人や唐人をこれに配しています。風景画には「長崎八景」がありますが、これはすでに長崎絵の特色がうすれ、江戸や上方の名所絵を思わせるものになっています。長崎絵の本領は、異国情緒をもった長崎の描写であり、外国趣味がその主なる題材となっています。蘭人と唐人を主としてロシヤ、アメリカ、イギリス、フランス、トルコ、朝鮮、槌鞘の各国人に黒人の人物描写、珍鳥やみなれぬ動物(ホルホラート・駝鳥・象・駱駝)の描写、蘭船・唐船をはじめとした他のいろいろな異国船の描写。それに異国の風習(阿蘭陀冬至・唐人蛇踊)と、長崎での異人の生活(阿蘭陀商館・唐人屋敷・丸山遊女の出代り)などがあります。この長崎絵と江戸絵を比較してみると版画技法の点でも大きな相違を認めることができます。長崎絵がもつやわらかな摺り上りは、中国版画の姑蘇版に共通するところが多く、その影響がいちじるしいです。また舶来の銅版画の影響もみられ、顔料も西洋絵具や用紙では唐紙を使用し、色はそのほとんどが原色を使い、簡単な彩色法です。江戸絵では竹の皮をかたく巻きしめて作製する「馬連」を使って摺りましたが、長崎絵では中国版画にならって馬の尾毛やたてがみをまるめて作った「馬連」を用いました。そのため江戸では紙を湿して強く圧力を加えて摺るのに対して、やわらかな摺り上りの長崎絵は、絵具の吸い込みが自然で、発色にさわやかな美しさをもっています。摺りのもう一つの特色は厚板をくり抜いてそれをあてがって摺る合羽摺りの技法がみられることです。精巧な江戸錦絵の技法が導入されて、素朴のなかに妙味が存在した長崎絵は次第に影を薄めていったのです。
このような内容・技法をもつ長崎絵の歴史を代表的板元を掲げて次に述べてみましょう。まず年代の最も古い板元は桜町の針屋で、板元の主人針屋与兵衛は宝暦四年(1754年)に没していますので、これを下限として享保頃までさかのぽり、その墨刷り手彩色の技法などからもこの年代が推定できます。現在板元名記入のものは神戸市立南蛮美術館に三点(蘭人・唐人・唐船を描いたもの)があるのみで、その影響は大きく、ながく長崎絵の題材と構図の基本線となりました。針屋と同じ年代の板元に東浜町の中島竹寿軒がありますが、これらに次いで古い板元が勝山町の豊島屋です。豊島屋は明和頃(1764年-1771年から現れ、天明頃(1781年-1788年に富島屋と家号を改め、文政中期にいたるまで四代つづいた老舗です。
初期は長崎絵を代表する優秀な作品を作り、彩色や摺法など後年では見られぬものを残しています。色摺りの初めを示す合羽摺りを併用したのが安永七年(1778年)頃からで、赤を多く筆彩で施して藍鼠を使用した配色と濃淡摺りの墨摺りが巧みにマッチしています。並行の横斜線を用いて陰影をつける方法、ひきしまった構図などにこの板元の特色がみられます。
同じ勝山町の文錦堂は、豊島屋の次に登場する板元で、寛政十二年(1800年)の墨・藍・茶の三色摺りの「阿蘭陀船入津之図」が処女出版で、化政期から天保にかけ最盛時代をすごし、嘉永の中頃まで存続しました。文錦堂といえば、長崎版画の代名詞の観をもつほど、舶来動物・年中行事・トピッタスなど長崎絵の題材のほとんどを描きました。合羽摺りや板摺りの色摺り版画にはすべて植物性顔料を用い、紅殻色の赤、黄土に近い黄、弱い藍の三色を基調として、素朴ななかにエキゾチックな感覚をあくまで保持しました。出版量もかなり多く、西洋画や中国色摺り版画の影響も無視できませんが、長崎古版画の最後の香りをふくよかに感じさせます。
享和元年(1801年)版の「長崎図」をもつ今餓冶屋町の大和屋は、文錦堂にややおくれて現れた板元で三代つづき、長崎絵後期の代表者といえましょう。文化十四年(1817年)頃磯野文斎という画家がこの板元を経営します。渓斎英泉に浮世絵を学び、文彩堂とも号し、江戸の摺り師久五郎と大阪で会い、ともども長崎まできて江戸絵の技法を長崎絵に導入しました。文錦堂の三色摺りを五、六色十数度の摺りに拡大し、複雑で豊富な色彩を洗練した技術で表現し、従来の平行線だけでない色面による量感の扱いなどに新生面を打ち出しました。画題では女性を登場させ、江戸絵風の美人や外国女性も描きました。長崎絵には落款がなく、絵師の名前を知ることができませんが、豊島屋二代伝七の店に天明二年(1782年)『海国兵談』の著者林子平が訪れ、四点の版画を制作させたり、文化六年(1809年)に没する文錦堂初代松屋齢右衛門は北虎と号し、安政六年(1859年)に没する二代俊平とともに絵を描き、ほかに文錦堂初期に唐人を得意とした敲月館や谷鵬、城義隣などの名が散見する。大和屋版には、シーボルトに愛された川原慶賀(1786年-1860年)や文斎(1857年)のほか、妻慈恩の名が知られます。また安政頃には梅香堂可敬の自画出版もみえます。大和屋の板元印のあるものは初期に多く、個人の落款のあるものは時代が下るといわれていますが、長崎絵の持ち味はその後期にはまったく色あせてしまいます。以上掲げてきた板元のほかに、東浜町の扇屋、船大工町の牛深屋(享和元年)刊の(長崎図)、勝山町の今見屋(「ヲロシヤ使節レザノフの軍艦ナデシダ号、文化元年」、同町の文松堂、梅香崎にあったと推定される梅香堂、ほかに笹屋、紺屋店、益水(本下町)、益屋、山上、活済堂、鄭華堂(本石灰町)、いづみや、栄寿堂(今銀冶屋町)、耕寿堂、竹寿軒(東浜町)、島原屋(恵美酒町)、綿屋などが知られます。長崎絵研究にはすでに長い年月がかけられています。黒田源次、永見徳太郎、池永孟、井上和雄、西村貞、小野忠重、野々上慶一の各氏などの論稿はその一つ一つの積み重ねに大きな足跡を残しています。
かくて長崎絵が、江戸絵の洗礼を受けて特殊な味わいを喪失した頃、安政六年(1859年)五月、幕府は長崎、神奈川、箱館の三港を開き、露・英・仏・蘭・米の五ケ国に貿易を許しました。ことに江戸に近い横浜の開港は人々の関心事となり、江戸の板元たちはこぞって横浜へ浮世絵師を派遣しました。エキゾチシズムを今や長崎に求めるものはなく、長崎絵に交替し横浜絵が新しくここに登場してくるのです。
富山版画
江戸時代の富山藩はわずか十万石で、越中の国のほとんどが加賀藩に領有されていました。今日一般に富山版画として紹介されるものは、その広い越中を背景に発達したため、越中版画と呼称しても差しつかえません。むしろ富山の売薬版画としての小さな概念だけでとらえようとするより、適切な名称であると考えられます。この富山版画の初期時代は不明の点が多いですが、色摺り版画ができるようになったのは弘化頃(1844年~47年)と考えられ、売薬版画に江戸の浮世絵師の名がみえますので、その技術は江戸からの導入といえましょう。次に村上清造氏の分類にもとづき考察を加えてみましょう。
宗教版画
越中の神社仏閣には中世以来の古い事蹟をもつものが多く、墨摺り版画としての宗教版画がより早く制作されました。神仏の御影・護符・牛王・縁起図一登山図などが摺られ、参拝人に配られました。なかでも立山の信仰は全国的に有名であり、多くの檀那廻りにはこれらの版画が必需品でした。天元二年(979年)の銘がある「雷鳥の図」の版木もありますが、正徳頃(1711年~6年)からの江戸期の作品が圧倒的に多く残っています。立山、立山の麓の芦嶮や岩嶮の祭事、立山と特に関係の深い不動尊をまつる大岩山、それに越中五箇山行徳寺関係などが、その題材となっています。
本草版画『本草通串』は和漢薬の内外文献を抜草した書物で、本草学者として有名な前田家十代藩主利保が著したもので、そこに掲出された原植物を示すため、薬用植物を採取し、これを藩の絵師、木村雅経・山下守胤・山下式胤・松浦守美などに写生させ、『本草通串証図』を作製しました。日本における植物図譜の優秀なもので、藩主自身の企画による御小屋摺りともいうべきもので、図画、彫刻、摺り、製本など当時の一流技巧をこらした作品でした。
売薬版画
富山の売薬は元禄三年(1690年)に始まり、年代を経るに従い多くの行商人を通じて発展していきましたが、そのため薬袋・預け袋・効能書き等が印刷によるため、その発達がおのずからもたらされました。しかも進物用にそえる版画も大量につくられ、富山浮世絵としての一ジャンルを形成しました。初期の弘化・安政頃(1844年~59年)には松浦守美の作品が多く、明治にはいると尾竹国一、尾竹竹埴と尾竹国観(ともに国一の弟)、水上如観(国一の弟子)の名がよく見出され、豊原国周・国信・国重・国春の江戸の浮世絵師も散見する。題材は芝居絵・武者絵・福の神など、明治には歴史画も加わります。板元も栗山暗清兵衛が最初といわれ、羽根屋又七などもあり、明治時代には高見順平、小泉重兵衛、笹倉好郎、四谷治平、中川、越中おぐらやなどが知られます。売薬の進物用が圧倒的に多く、画風には上品さはなく、大衆的な誰にでも親しめるムードが特色です。
俳画
近世にはいり越中に来遊した知名な俳人には、貞享年間(1684年~87年)に大淀三千風、元禄二年(1689年)に芭蕉がいます。芭蕉の門弟となった越中人に、井波瑞泉寺十一代住職浪化がおり、このため蕉門の大家が多く来越し、大衆のなかに俳句が次第に普及し、文化文政頃より越中版による俳書がかなり制作されました。安政三年(1856年)『俳諧多磨比路飛』、四年『俳諧画讃百類集』、六年『八重すさび』等がそれで、他に俳画の一枚摺りも多くあり、松浦応真斎守美(1824年-1886年)の作画が多いです。
その他<
元禄頃より藩札や富籤札、講札、頼母子札が墨摺りで制作され、色摺り版画になってからは、富山名所「越中富山神通川船橋之図」や温泉宣伝用の「黒辺川辺の黒薙温泉」など、多方面に版画が逆用されたことがわかります。
このようにみてきますと、富山版画は、立山を中心とした宗教版画に始まり、江戸時代の末頃より、一枚摺りでは大衆を対象とする売薬版画や富山名所絵があり、版本では知識層を対象とする学術書や俳書の出版があるわけですが、前者には歌川豊国門下の系統をひく絵師と後者には狩野派系統の絵師がそれぞれ見出されます。また享和頃には富山藩には判木方がおかれた様子で、彫り師として古川紋次郎(寛政頃)、荻田永治(文政頃)、その他十数名が知られ、版画の板元と異にした越中木版本の書林として貫道堂、紅屋伝兵衛その他数軒を掲げることができます。このように雪に閉ざされる富山の地に版画が盛行したことは、富山がちょうど江戸文化と上方文化の分水嶺的地位にあったためではないかと思われます。富山版画は文化史的観点より考察すべき問題を多く抱えているのではないでしょうか。
上方絵
ここで述べる上方絵は、天明期(1781年~88年)以降における京都及び大阪で刊行された版画をいいます。
京都大阪の地は、近世初期の芸術を育てた所で、貴族や富豪を対象とする芸術を発展させていたため、江戸のような新開の地がもちえた庶民対象の芸術は育ちにくい土壌でした。近世初期肉筆風俗画を生んだ上方でしたが、その描く内容が等しいにもかかわらず、肉筆に重点がおかれて、版形式の絵画はきわめて軽視されてしまったのです。明和時代に始まった江戸錦絵が、上方で流行するのは、二十年ほど遅れた天明期であっ さがた。もともと版技法は上方のものであり、嵯峨本、蒔絵師源三郎、吉田半兵衛など元禄前後の絵入り本の発展期につづき、肉筆にも秀でた享保期の西川祐信は多くの絵本に傑作を残したが一枚絵はなく、その後も大阪の月岡雪鼎のような肉筆に健筆をふるうものが出たが、版画方面ではふるわず、江戸版画界が長足の進歩をとげてゆくのと正反対の現象を呈しました。しかしここで注目しなければならないことは、遠近法による浮絵が京都の円山応挙によって描かれ、そして延享頃(1744年~47年)から木版によらない色摺り、すなわち合羽摺りが発達することです。さて江戸の錦絵の影響をうけて作られた大阪の版画を浪花錦絵とよぷ。この浪花錦絵の研究でまとめた『上方絵一覧』は昭和四年の発行ですが、著者黒田源次博士は次のような系統に分類しました。
流光斎の作画期は寛政から文化(1789年-1817年)にわたりますが、その役者の表情には、江戸役者絵とは異なる自己独自の表現をとりました。これには天明二年(1782年)大阪の絵師翠釜亭によって描かれた役者似顔絵の絵本『翠釜亭戯画譜』との関係が考えられ、四年に刊行された流光斎の代表的絵本『旦生言語備』はその影響の人なることを如実に物語っています。松好斎は流光斎よりさらに上方的なムードを横溢させ、寛政十二年(1800年)刊の『戯場楽屋図会』や享和二年(1802年)則の『俳優児手柏』などの優品を残しましたが、その門人に春好が出て、多くの門人を擁し一派を形成していきました。春好は文政初期(1818年~20年)に北斎の門下となり、春好斎北洲と改め、文化中期から北斎風の加味された上方絵独自な類型が定まり、天保初期頃(1830年~33年)まで役者絵や読本の挿絵に多くの作品を残し、名実ともに上方絵界の第一人者となりました。画系の祖である芦国は、須賀蘭林斎の門人で蘭英斎、青陽斎、狂画堂の号をもち、文化中期頃より絵入り脚本や役者絵を多く描き、寿好堂よし国、戯画堂芦幸、浜松歌国など門人が多く、そのなかでもよし国にはさらに多くの門人がつき、一大門葉を形成していきました。
北斎門下で女婿にもなったことのある有名な柳川重信が文政五年(1822年)頃、短期間ではありましたが、大阪に滞在したことに始まります。当時大阪に江戸風の錦絵が流行したときでしたので、来り学ぷものも多く、重春、雪信、国直の門人ができました。重春は、初め梅丸斎国重、崎陽亭国重とも称し、文政九年(1826年)に国重を改め柳斎重春といい、また玉柳斎とも号しました。文政末から天保にかけて絵本がすこぶる多く、芝居・の看板絵も描いたといいます。門人には重直、重房、重広がいます。当時全盛期を迎え、江戸錦絵界を制覇していた歌川派の影響を受けた系統です。まず初代豊国の門人国広や二代豊国の門人国鶴などは、浪花で作画し、直接指導をしました。国広は前述の重春の初めの師であり、丸丈斎、江南亭などの号あり、文政から天保末までの作画期をもち、門人に国平がいます。国鶴は天保中期頃に活躍した人です。
国貞の門人として浪花錦絵に関係をもったものには、貞広、貞升、貞次があります。貞広は歌川を名乗り、五蝶亭、五楽亭と称し、三谷貞広とも記し、役者絵の他に風景画もみられます。門人に五椋亭広貞があり、多作をもって知られます。貞升は歌川五蝶亭、一樹園と号し、師国貞の豊国襲名後作画期は天保から嘉永に及び、特に天保期の作品が多く肉筆画にも秀でて、役者絵の外に風景画を描きました。その門下とみられる人々は十人以上も知られ、歌川派を大阪でひろめた功は大で、なかに幕末から明治初年にかけてすぐれた絵師であった長谷川貞信を出したのは注目されます。貞信は美人・役者・風景の各領域で優れ、その子小信は二代目を襲名しました。
国貞と同門の国芳の系統もまた影響を及ぼしています。国芳の直門に芳梅があり、さらにその門下生に梅雪、芳峰、芳英、芳滝が見出されます。芳梅は一鶯斎と号し、この門下は、国貞系より幕末から明治にかけて栄えました。
特に芳滝は知名度が高く、その門人には明治の初め洋風画の京阪名所図絵を描き、東京の小林清親に匹敵する京都の芳国が異彩を放っています。
以上大阪版画界の発展過程を述べたのですが、これは江戸版画界の影響下にあくまでも拡大していったもので、当時江戸の版画そのものがすでに衰退期を迎えているときにあたり、上方独自の面を出しつつも、それ以上に芸術性の高いものは制作できませんでした。その意味では浪花錦絵をして地方版画の一つと考えざるを得ません。ここで一言しておきたいのは、江漢・田善が没し雷洲にいたり芸術的な衰えが大になる江戸銅版画にかわって、京阪に芸術的というより実用的な銅版画が栄えたことです。藤若子などの画人が存在して鉱物動植物図の銅版画を制作しました。
最後に江戸版画ではほとんど用いられなかった合羽摺り(墨摺りの上に色の部分の型紙を使用して彩色する)は、上方・長崎に多く用いられ、中国版画の影響をまだ色濃く残存させていますが、この技法から脱皮した江戸版画に一段と発展した近世芸術の花が咲いたことは否定できません。