 解説
解説 写楽 Sharaku 解説
写楽 sharaku東洲斎写楽この浮世絵師ほど多くの憶説につつまれ、数多くの研究家によって、その巨峯を踏破せんと試みられたものはありませんでした。出生をはじめとして、いかなる生い立ち、画界へのデビュー...
 解説
解説 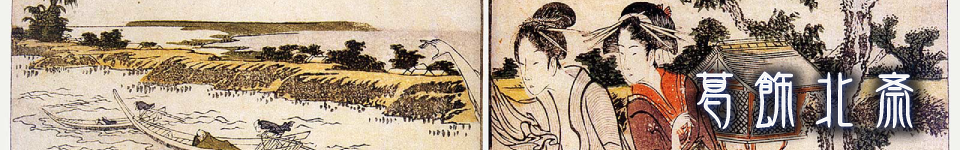 解説
解説  解説
解説  解説
解説  解説
解説  解説
解説 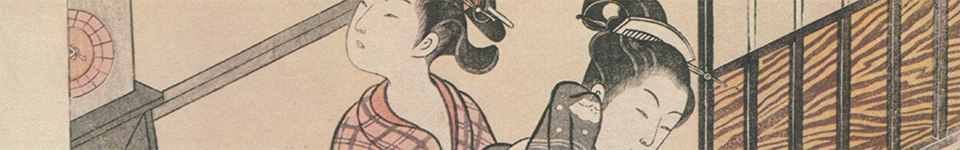 解説
解説  解説
解説  解説
解説  解説
解説  解説
解説  解説
解説